筆者のCD-R書込み環境
はじめに
大事なCDを車で使いたくはありません。それでCD-Rに焼いて聴いています。
MDからCD-Rに変えた当初、音の酷さにがっかりしたのがCD-Rにハマルきっかけでした。幸いなことに、The COLT-T's webcomsというHPに巡り合うことができ、集う皆様のおかげで、だいぶ納得がいく音になりました。
以下の3つの環境がありますが、最近はデュプリケーターばかりになっています。
- デュプリケーター(P-ATAドライブを用いる場合)
- パソコン(SCSIドライブを用いる場合)
- 業務用CDレコーダー Marantz CDR630
デュプリケーター
 P-ATAやS-ATAドライブでは究極の選択だと思います。デュプリケーター専用ケースに組んでいます。ちょっと大きくなりますがパソコンケースでも組めると思います。
P-ATAやS-ATAドライブでは究極の選択だと思います。デュプリケーター専用ケースに組んでいます。ちょっと大きくなりますがパソコンケースでも組めると思います。
- デュプリヘッドはACARDのARS-2022D
- ドライブはその都度気ままに選択します。書き込みドライブは等速書き込みできる古いのが好みです。(画像は、MP-7040AとPX-1610TA)。
読み込み速度は8倍速、CD書き込み速度は1倍速、バーンプルーフはOFF、の設定で使っています。どちらもこのデュプリヘッドで設定できる最低速です。この設定でも、最低書き込み速度が4倍速のドライブは4倍速になります。
スイッチング電源ながらケース付属の電源もなかなか捨てたもんじゃないので、わざわざ自作しなくても良いかな?という感じです。放熱が気になりますが、ケースファンは停止させています。連続で使用しないなら問題ないんじゃないかと。放熱重視で5ベイのケースも考えたんですが、大きくなってしまいますし・・(^^;;
パソコン
以前、頑張っていた時の環境ですが、ここ数年の稼働実績はありません(笑)。CD-Rもあまり焼かなくなりました。いづれ解体しなければなりませんね。以下は昔のままですが、記録のため残しておきます。
好ましいSCSIドライブ用のデュプリケーターがあればわざわざパソコンを使う必要もないのですが、気に入らないのではしかたありません(笑)。
最近のパソコンは不必要に高スペックでノイズが多いので、なるべくロースペックのパソコンを使っています。
最近のOSは重過ぎるので、なるべく軽いOSにしています。
PC電源はスイッチングタイプの中でも一段とノイズが多いようなので、リニアタイプの電源を自作しています。
つまり、オーディオまたはデュプリケーターを手本として、なるべく近づけるようにしています。
マザーボード
 486のマザーは中古でも少ないですが、PCIスロットのあるものに限定して入手しています。VLBを持つM/BやISAだけのM/Bはさらに古いですし、ISAのSCSIカードがいまいち使いこなせなくて・・(^^;;
486のマザーは中古でも少ないですが、PCIスロットのあるものに限定して入手しています。VLBを持つM/BやISAだけのM/Bはさらに古いですし、ISAのSCSIカードがいまいち使いこなせなくて・・(^^;;
メーカー不詳、型番 terminator、ATマザーです。External CacheをDisable。
ディスプレイ
書き込みが始まり、後は焼き上がりを待つばかりとなったら、ディスプレイの電源ケーブルを抜き、ディスプレイケーブルもPCから外しています。
PC本体のノイズばかりとりざたされますが、ディスプレイのノイズも大きいです。本来書き込みには不要なものであり、電源環境やディスプレイによってはかなりの効果があります。詳しくは、パソコンでノイズ測定?のディスプレイ編をご覧下さい。
HDD
 CompactFlashを、ARTMIXのCF PowerMonsterで変換して、SCSIドライブとして使っています。
CompactFlashを、ARTMIXのCF PowerMonsterで変換して、SCSIドライブとして使っています。
ドライブのインターフェース
ALL-SCSIです。ATAPIドライブは、ACARDのAEC-7722UでATA-SCSI変換して使うこともあります。
OS
古いですが、Vine Linux 1.1をテキストモードで使っています。パソコンに負担をかけるGUIは用いません。
詳しくは、「コマンドでCD-R」をご覧下さい。
ライティング・ソフト
Linuxの定番、CDDA2WAVとCDRECORDをコマンドで使っています。Vine1.1用にビルド。
書き込みドライブ
愛用ドライブを紹介します。
新旧いろんなドライブがありますが、好みにあったドライブを捜すのは難しいです。筆者はDVDドライブよりCD-Rドライブ、ATAPIよりSCSI、高速より低速ドライブ、という選択になっています。本当は最も好みなのはCDW-900Eですが、天邪鬼の筆者としては当たり前すぎて面白くないので避けています(笑)。CDRECORDが使えないのもネックです(DOS環境でDAO.EXEは使えました)。
SONY CDU924S
 SCSI 2倍速。ナチュラルで腰の据わった音で情報量も豊富ですが、中低域の音の塊が強烈で周波数バランスを崩しています。筆者は改造するためのベースにしていますが、無改造なら他のビンテージドライブの方がいいでしょう。ファームも1.xが多く、最近のメディアはまず使えません。
SCSI 2倍速。ナチュラルで腰の据わった音で情報量も豊富ですが、中低域の音の塊が強烈で周波数バランスを崩しています。筆者は改造するためのベースにしていますが、無改造なら他のビンテージドライブの方がいいでしょう。ファームも1.xが多く、最近のメディアはまず使えません。
発振子をクリスタル化したら高域が延びて少し聴きやすくなりました。
SONY CDU948S
 SCSI 4倍速。いちおうビンテージドライブの仲間ですが、コストダウンのため華奢な作りです。珍しいプラスティックシャーシーのためか、中〜低域の腰が貧弱です(と思っていたんですが、CRX100も似た音だったので、この時期のSONYはこんな音なのかもしれません)。それでも、InternetStationで「ライブを思わせる澄み切った艶やかな音質」と評された音は、この後のドライブでは聴けません。メディア対応は924Sより広いです。
SCSI 4倍速。いちおうビンテージドライブの仲間ですが、コストダウンのため華奢な作りです。珍しいプラスティックシャーシーのためか、中〜低域の腰が貧弱です(と思っていたんですが、CRX100も似た音だったので、この時期のSONYはこんな音なのかもしれません)。それでも、InternetStationで「ライブを思わせる澄み切った艶やかな音質」と評された音は、この後のドライブでは聴けません。メディア対応は924Sより広いです。
素のままでは元気の良い個性的な音質ですが、お試しリジッド化したら素直な感じに変化しました。
Plextor PX-R412C
 SCSI 4倍速。8倍速の820Tを長く使っていましたが、820Tでは淋しいところが淋しくならず、やっぱスピンドルモーターの違いは大きいと思います。PlexMasterもこちらを元にすれば良かったのに・・(笑)。中域にクセがあるので、ローディングメカなど外してスッキリした形でリジッド化してみたいです。
SCSI 4倍速。8倍速の820Tを長く使っていましたが、820Tでは淋しいところが淋しくならず、やっぱスピンドルモーターの違いは大きいと思います。PlexMasterもこちらを元にすれば良かったのに・・(笑)。中域にクセがあるので、ローディングメカなど外してスッキリした形でリジッド化してみたいです。
ケース
通常のベアドライブの場合、市販のケースはどれも柔に思えるので、コーリアンボードに底付けしています。
お試しリジッド化したものは、ケースがありません(笑)。いずれがっしりしたケースに収めたいですけど、いつのことやら・・。
メディア
フタロシアニンよりシアニンを好みます。アゾは好みません。手持ちの中で好きなメディアは誘電の8xとPrimeDiscの12xです。
テスト焼きは太陽誘電32倍速が多く、本焼きは、各社8〜32倍速のメディアを適当?に選択します。
juubee's おぼえがき © by juubee
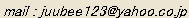 作成 2003/9/17 最終更新 2017/12/19
作成 2003/9/17 最終更新 2017/12/19
