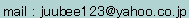野菜つくり
定年近い頃から始めました。自然農法です。手探りしているうちに14年目になっちゃいましたね。全然上達していないけど(笑)。
音楽CD-R
かつてのメインでした。最近やってないので古い内容が多いですが、一応記録のために残しておきます。いづれ、時代に合わせてシンプルに書き直す時が来るでしょうか (^^ヾ
--------------
ある時ふと、デジタルコピーでもずいぶん音質が違うことに気づいてしまいました。
ここは、そんな筆者の取り組みを徒然に綴るページです。
コマンドでCD-R
気まぐれコンテンツ
測定のページ
CD-R書き込みとパソコン環境
音楽CD-R初級者向け
初級者のためのQ&Aそれなりに音質が良い音楽CD-Rの作り方
音楽CD-Rの実際知識
音楽CDのリッピングと音質
(CD-Rと言うより、PCオーディオ向け)
その他
© by juubee
HP開始 2003/6/11
雑記以外の最終更新 2016/7/26